クロモリラレーのパンク修理

水元公園の紅葉ポタリング帰りのパンク。
久しぶりではありますが、いつパンクするかわからないのがパンク。
個人的にパンクに見舞われる確率が高いと思っていますが、原因の一つは軽量タイヤ&チューブを使っているところにあることは確かです。
ですが、今使っているブリヂストンとパナソニックチューブの組み合わせは、性能的にも軽量快速だし、耐パンク性能もここまで約2年半。
コロナで走行距離が短いとはいえ、そこそこ持ちこたえてきました。
ですが、いつかは来るパンク。
今回は水元公園から帰路の途中、応急チューブ交換で無事帰宅。
というわけでさっそく、パンクした翌日自宅でパンク修理スタート!

チューブのパンク修理
パンクしたチューブは現場で予備チューブに交換して持ち帰ってきています。
ツールボトルから取り出して作業開始
パンク箇所を確認する
ツールボトルからパンクしたタイヤを取り出し少しエアを入れ、水を張ったタライでチューブのパンク位置を探します。
 おだケン
おだケンありました!
バルブのすぐ隣から、泡がプクプク浮き上がっています。


この1箇所だけのよう!
ゴムノリを塗ってパッチを貼る
水気を拭き取り、パンクした部分をヤスリで削ります。
もちろん荒目のサンドペーパーでもOK。




パッチですが100均のママチャリ用はデカ過ぎる!
ロードバイク用のサイズの小さいパッチがホームセンターで売っていますのでそれを活用すると良いです。
私も近所のホームセンター自転車売り場で買ってきました。
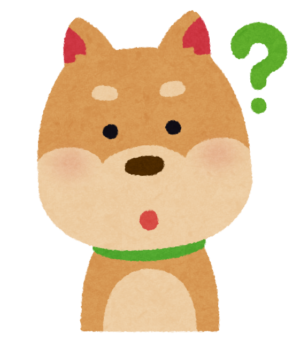
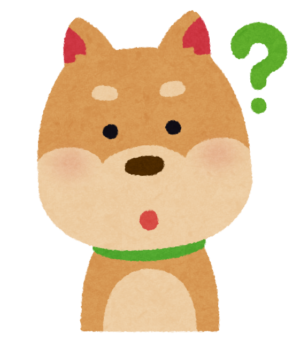
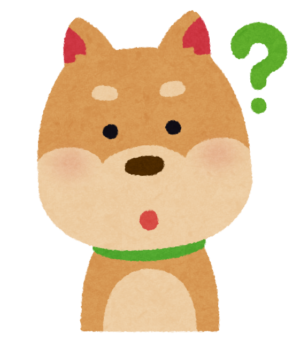
値段は覚えていない・・・$
チューブの穴の空いた周囲を削り取ったら、パンク修理用ゴムノリを広めに塗る。
1分ほど乾かしたら、パッチを貼る。




パッチのフィルムを剥がして、穴の中心に貼る。




アルミ箔を剥がす。
パッチがチューブに張り付くよう、指でグイグイ力をいれ圧着する。




エア漏れがないかタライで再確認
エアが漏れないか、もう一度タライで確認。
ここでもし、パッチから漏れていたらパッチを指で少し剥がしてゴムノリを補充。
作業的にはそれほど難しくないものです。
100均でパンク修理セットを購入プラス、ホームセンターでロードバイク用パッチと追加でゴムノリを買っておけば次のパンク修理もOK。(100均パンク修理にもゴムノリはついていますが小さい)
5分ほど乾かしたら、タイヤに入れますが私の場合もう一手間かけます。
パナレーサー・パウダー
パウダーを塗りつける
過去にチューブがタイヤの内側にベッタリ張り付いて一苦労したことがありました。
それ以来、このパウダーを使っています。
必須ではありませんが、一度苦労をすると二度はしたくないのでこのパウダーを使っています。
使い方は、付属のスポンジでパウダーを飛び散らかさないようチューブに静かに塗っていくだけ。
ネットで、「ビニール袋にパウダーとチューブを入れ唐揚げ如くふればクマなく濡れる」という紹介がありやってみましたが、そこらじゅうパウダーだらけ。おまけに、タイヤまで白くなってしまうので、このやり方はオススメしません。

付属のスポンジでうす〜く塗ることをオススメします。





ースポンサーリンクー
パンク修理の続き
パンクした後輪を外す
今回パンクして予備のチューブが入っている後輪をフレームから外します。
そして、100均タイヤレバーでタイヤをホイールから少しずつ外していく。
片側全周タイヤが外れたら、チューブを取り出します。




修理したタイヤに入れ替える
修理したチューブを少し膨らんだままタイヤに入れます。
バルブをホイールに刺し、バルブを起点にして、チューブをタイヤの中に入れていきます。




途中からエアを抜いた方が楽かもしれません。
タイヤをホイールにはめる
チューブがタイヤにおさまったらチューブのエアを抜いて、タイヤをホイールに嵌めていきます。
これもバルブを起点にして嵌めていきます。
最後は少し硬いですがタイヤを引き伸ばすようにして嵌めていけば、(新品タイヤでなければ)苦労しないと思います。
エアを少し入れてタイヤを揉む
再度チューブが少し膨らむ程度エアを入れたら、タイヤを横から揉んでいきます。
チューブがタイヤに挟まっていないか確認しながら揉んでいきます。
チューブをタイヤの中央に寄せていく。


エアを規定値まで充填
最後は、エアを入れます。
私の場合は8barと決めています。
特段の理由はありませんが、これ以上入れるとお尻が痛くなるので・・・


ホイールをセットする
最後にホイールをフレームにセットします。
フレームのセンターに合うよう、ブレーキシューの左右の隙間が均一になるように調整してクイックレバーを閉めてください。
クランクを回してチェーンとスプロケを噛み合わせれば終了!


後片付け
最後は後片付け。
予備のチューブのエアを抜いてツールボトルに入れます。
その他、工具もボトルに戻す。
使用したCO2ボンベも入れ替えて、作業終了!
おわりに
手順は、前回の記事でも紹介していますので、今回は簡略(?)しています。
特に難しいものではありませんが、しっかり確認しないと事故の元になりますので注意が必要です。
パンクは嫌になる程見舞われていますが、自転車に乗る以上必ず経験するもの。
特にロードバイクは長距離長時間を走りますのでリスクが高いですが、事前の準備と対処方法を心がけていれば窮地には至りません。
路面・段差・落下物に注意して安全運転で楽しみましょう!












